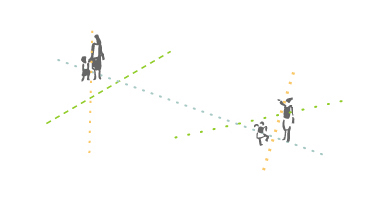

2011年度第4回研究会

2011年度第4回研究会
日時:2012年3月30日(金)13:30-19:00 場所:本郷サテライト7階
上杉妙子(AA研共同研究員,専修大学)
「独身兵士と既婚兵士―国家政策から見た兵士の婚姻地位の両義性―」
妙木忍(AA研共同研究員,東京外国語大学)
「梅棹忠夫の女性論・再考」
<発表要旨>
兵士の婚姻地位と民軍関係―植民地インドを中心として―
上 杉 妙 子
専修大学
本発表では、兵士の婚姻地位と民軍関係との関連について検討した。具体例として、19世紀後半の英領インドにおける兵士に対する婚姻政策を取り上げた。記述と分析に用いたのは、公文書と先行研究、私自身による収集データである。
民軍関係とは、civil-military relationsに対応する日本語の訳語の一つであり、民間組織や民間人、文官政治家と、軍隊ないし軍人との関係をさす。(もう一つの訳語は政軍関係である。) 少なからざる軍人が比較的高い生殖能力をもつ若い男性であることを考えるならば、民軍関係を考える上で、兵士の配偶関係・愛人関係に注目する必要があるのではないか。
検討の結果、以下のことが明らかとなった。
第一に、英領インドでは、将兵の階級や人種によって婚姻規制を差異化していた。
まず、英国人兵卒については婚姻許可を制限していた。これは、経済的効率(既婚兵士に与える手当の節約)と軍事的効率(独身男性の高い戦闘能力)を重視したためであった。しかし、その結果、植民地支配を支える人種の維持にとって多くの問題をもたらした。独身生活を送ることを余儀なくされた兵卒たちは、男色や買春に走り、性病に罹患した。また、結婚許可をあたえられなかった兵士の妻子は、夫の死後、寡婦手当をもらうことができずに、インドで路頭に迷うこととなった。こうして生まれた「貧乏白人」の存在は、「支配人種」であるべき白人の地位を脅かすものであると考えられた。社会進化論的観点からみた植民地支配の道徳的正当性を揺るがしかねないとされたのである。
つまり兵士が独身であることは、植民地支配にとってメリットとデメリットがあったのである。
次に、植民地における白人エリートの一角を占める英人士官については、階級が上がると結婚していることが好ましいとされた。一家の長であることが、軍隊の階級組織を維持するための指揮官として好ましいと考えられていた。また、結婚する際には、同じ人種の女性と結婚されることが好ましいとされた。これは、支配人種とその生活様式を維持するための境界作業として、士官のみならず、他の英国人エリートについても見られたことである。
最後に、現地人兵士についてみる。英国側は、現役兵士の結婚については規制を行っていなかったようである。しかし、ネパール人兵士であるグルカ兵は、自らが、通婚範囲の自主規制を行っていた。これは、第一に、雇用の超世代的連続を図ることを目的としていた。グルカ兵は、英国側が、駐留地における民軍関係の調整の都合と有能な兵士を採る都合上、植民地人民と異なる民族を求めていたことを熟知し、自らが「グルカ」を創造していたのである。第二には、グルカ兵内部の統制のために、民族的同質性を維持することが重要であると考えていたことによる。
結論を述べる。19世紀の植民地インドにおいては、軍人の婚姻地位は、軍事的効率や経済的効率、民軍関係、雇用の超世代的継承、内部統制に影響を与えると考えられ、何らかの規制が実施されていた。つまり、兵士の婚姻地位は植民地支配の帰趨にかかわると考えられていたといってよい。しかし、兵士たちの婚姻の取り扱いは、すべての兵士に同等というわけでは決してなかった。軍隊の階級や出自により異なっていた。そのことは、19世紀後半の植民地インドに、階級や出自により男性たちの役割を差異化する構造があったことを如実に示すものであると言えよう。
梅棹忠夫の女性論・再考
妙木忍
東京外大AA研ジュニアフェロー
梅棹忠夫は1950年代に女性についての論考を数多く発表した。それは、『梅棹忠夫著作集 第9巻 女性と文明』(1991)に収められている。半世紀を経た今日、氏の論考の歴史的意義と現代的意義を再検討することが本発表の目的である。
これらの論考が書かれた時代は、高度成長期とも重なり、「家族の戦後体制」(落合恵美子による語)にあった。これは戦後から1975年ころまでを指し、落合によれば、女性の主婦化、再生産平等主義(皆が結婚して子どもを二人くらい産む家族のあり方)、人口学的移行期世代(1925年~1950年生まれ、人口が多かった世代)が担い手、という三つの特徴がある。梅棹の女性論が書かれたのは、まさに主婦が大衆化し多数派となる時代であった。その時代に主婦役割を否定した氏の論考は、賛否が渦巻き、主婦からも反発が生まれた。
1959年に書かれた「妻無用論」と「母という名の切り札」は私が氏の主要論考と考えるものであり、第1次主婦論争に、後に研究者によって、含められている。歴史をふりかえれば、主婦が大衆化する過渡期に書かれた梅棹論と、主婦が衰退する過渡期に書かれた1990年代後半の石原里紗論は、主婦役割の否定という点で類似している。ちょうどその二つがあらわれた時期は、近代家族の成立と終焉の時期に一致すると考えることもできる。主婦役割が自明とされた時代にそれを相対化した梅棹論を、再検討したいと考えたのである。
「妻無用論」は、結婚することと主婦役割を担うことをイコールとはせず、それが分離しうる(主婦役割とライフコースが独立したものであることを示唆する)視点を取り入れている(「女が妻をやめるというのは、なにも結婚しないということではない」)。また、結婚という制度を「なかなかきえさるまい」とした。しかし、「妻という名のもとに女に要求されたさまざまな性質は、やがて過去のものとなる」と、主婦役割を相対化し、それ自体が歴史的な産物であることを指摘している。また、「男と女の社会的な同質化現象は、さけがたいのではないだろうか」と予想している。
これら4点の指摘は、今日から見ても注目に値する。これらが今日現実となっているかどうかを判定することは難しいし、また判定することに意味があるかどうかは議論があると思われるが、2000年代に入り、(主婦役割よりも)結婚や出産などが論点となった「負け犬」論争の出現や、性別役割分担意識の通時的変化は、一つの指標になるかもしれない。
だが私がより注目したいのは、「男と女の、社会的な同質化現象」という論点である。家事や育児や介護などを、広義の意味でケアと呼ぶならば、ケアをめぐって、男女間には今日も非対称性がある。男性も女性もケアしたいときにケアすることを十分に選択できているだろうか、あるいは、ケアすることを強制されている場合があるとすればそれはいかに解決できるだろうか、という論点に将来的にはつながるだろう。理想のライフコースと予想するライフコースの不一致問題をあつかった岩澤美帆氏の研究を手がかりに、今日の女子大学生のアンケートを分析した。理想と予想の不一致が起きる場合、理想と予想が一致する場合、社会制度の不備や充実(への変化)なども指摘された。理想と予想の乖離の内容とその理由に、今日の問題点を見出そうとした。
だが、梅棹論の再検討という点からすると、梅棹論が生まれた背景、論考の内容の分析、当時の人々がそれをいかに読んだのか、今日の大学生がそれをいかに読むか、などの分析こそが必要であった。これを本発表の限界とし、今後の課題と位置づけることにしたい。
DATE : 2013.03.04

2011年度第3回研究会

2011年度第3回研究会
日時:2011年11月12日(土)13:30-18:30 場所:本郷サテライト5階
馬場淳(AA研共同研究員,東京外国語大学)
「ウソと縁:あるホームレス的存在者の虚実」
花渕馨也(AA研共同研究員,北海道医療大学)
「移民と故郷のつながり-マルセイユにおけるあるコモロ人女性の別れと再会-」
<発表要旨>
ウソと縁――あるホームレス的存在者の虚実――
馬場 淳
東京外大AA研ジュニアフェロー
本発表の目的は、日本の埼玉県O市に生きる一人のホームレス的存在者(Sと呼んでおく)をとりあげ、彼が退職後の人生をいかに構築しているのかを縁の観点から検討し、そのうえで従来の縁観とは異なる縁のあり様を考察・提示することである。
具体的な事例の検討に先立ち、まずは先行研究から本発表に関わる論点を二つ抽出しておくことにしよう。一つは「アジ―ルとしてのホームレス」という視点である。これは、ホームレスになることが選択的であり、これまでの人生に関わる縁をすべて切ることによる自由の獲得という、積極的な意義を含む。二つ目は、ホームレスに見られるウソの問題である。ホームレスたちの中には、偽名を用い、偽りの人生を構築し、その(ウソの)なかに生きる者がいる。そしてこれら二つの視点は、連関している。すなわちホームレスたちが積極的に見い出し、入り込むアジールの世界とは、これまでの人生とはまったく異なるリアリティをもつ世界だということである。
本発表で取りあげるホームレス的存在者Sも、これまでの人生に関わる縁をすべて断ち切り、偽名を名乗り、まったく新しい人物として世界を生きている。発表者は、彼がアジールとして生きる埼玉県O市のストリートを対象に、彼と二人の女性の人間関係に主たる焦点を当てる。女性たちとの関係において、Sは過去の経験や情報資源を脱文脈化しながら、虚偽の世界を都合よく再構成してみせるが、それは決して一貫したものではない。時間の経過とともに、二人の女性(および発表者)はSの虚構性(ウソ)に気付いていく。結局のところ、誰にも「Sとは一体誰なのか」「Sの人生や生活はどのようなものなのか」が理解できないものとなってしまった。それでもなおSは、何が真実(またはウソ)なのかを明言しないことによって、真実や理解にもとづく他者との関係性を不断に留保し続けているのである。
このSの姿勢は、「常識」的な縁とは異なる縁のあり方を考えるうえで示唆的である。というのも、Sの姿勢とは「誰かにわかってもらう」という人間の実存的な欲求を拒否しつづけるものであり、真実=個人の本質を想定・追究する近代的な関係構築の発想とは真逆のものだからだ。Sが他者とつなぐ縁とは、自分および相手がどういう人間であるかを理解し合う前提にたたない縁なのである。団塊の世代に属するSが退職後の「第二の人生」として生きる世界は、これまでの人生から完全に切り離されたアジールであり、同時にSと他者がつながるあり方(縁)そのものが異なる独自の世界といえるのである。
Regroupement:マルセイユにおけるあるコモロ人女性の移動と縁
花渕馨也
(北海道医療大学)
移民が移民先に家族を呼び寄せ、共に暮らすことを実現する移民の「家族再結合」(Regroupement)は、「家族は共に暮らすのが望ましい」とする国際的理念や、フランスの法によって保障される権利である一方、移民規制が強まる中で、例えばDNAによる血縁証明など家族再結合の条件を厳格化したり、非正規移民の家族が分断されたりするケースも出てきている。そうした中で、コモロ系移民は、フランスの「出生地主義」による国籍制度や、家族に対するフランスの法的制度をうまく利用しながら、さまざまな裏の戦略によって家族の結合を実現させている。また、家族再結合の実現には、故郷との強い社会的紐帯を維持し、移民の相互扶助的関係を生み出している同郷村のアソシアシオンによるサポートが存在している。
本発表では、東アフリカのコモロから南仏マルセイユに移住してきたあるコモロ人女性のライフヒストリーについての検討から、コモロ系移民による家族や故郷との再結合の戦略と、そうした動きを通じて再編成されつつあるコモロ社会における村社会や家族の変化について具体的な考察を行った。
DATE : 2013.03.04

2011年度第2回研究会

2011年度第2回研究会
日時:2011年7月23日(土)13:30-19:00 場所:本郷サテライト5階
小池郁子(AA研共同研究員,京都大学)
「オリシャ崇拝による縁の形成―アフリカ系アメリカ人の社会宗教運動と「シングル」」
新ヶ江章友(AA研共同研究員,名古屋市立大)
「男性同性間の性関係からパートナーシップへ―クィア家族を再考する―」
<発表要旨>
人種と性が交錯する「家族」
―アフリカ系アメリカ人のオリシャ崇拝運動が紡ぐ縁―
小池郁子
京都大学
本発表の目的は、アメリカ合衆国の正常(健全)な家族像から逸脱しているとされてきたアフリカ系アメリカ人の家族、とりわけ社会的病理として捉えられてきたアフリカ系アメリカ人男女の「シングル」に注目し、そこで人種と性がいかに交錯しているのかを検討することである。具体的には、アフリカ系アメリカ人の家族にまつわる事象の何が問題とされてきたのかを述べ、そうした問題化と米国が正常として提示する家族像との関わりを明らかにする。そのうえで、オリシャ崇拝運動にみられる宗教的疑似家族(イレile)や、家族に関する価値観、性役割、性規範などを取り上げ、それらとアフリカ系アメリカ人の家族問題との関連性について考える。
なお、本発表で着目するオリシャ崇拝運動は、アフリカ系アメリカ人の男性、オセイジェマン・アデフンミ一世(1928-2005)によって結成された。この運動は、1950年代、60年代前半、公民権運動の潮流が高まるなか誕生したアフリカ系アメリカ人の社会運動の一つとして位置づけられる。運動の拠点は、米国南部にある「アフリカン・オヨトゥンジ・ビレッジ」である。オヨトゥンジ村は、アフリカ系アメリカ人がオリシャと呼ばれるヨルバの神々を崇拝し、ヨルバの伝統的な生活様式を再現しようとした一種のコミューン(生活実践共同体)である。
アフリカ系アメリカ人の家族は、経済学、社会学、歴史学、都市人類学、心理学をはじめ、様々な領域において分析されてきたが、そうした分析にはある種の共通点をみいだすことができよう。その共通点とは、アフリカ系アメリカ人の家族を性の逸脱や男性不在の家族という視点から問題化、あるいは説明してきたということである[cf. ブラッドリー 2010(2008)、リーボウ 2001]。そこでは、アフリカ系アメリカ人男性は白人女性の純潔を守るため、白人の監視下におかれるべき野蛮な存在として位置づけられている。一方、アフリカ系アメリカ人女性は、男性を精神・聖、女性を肉体・汚れとみなす米国の価値観のもとで、貞淑な白人女性とは異なり、白人男性を誘惑する淫らな女性というように、二重の負のラベルを課されている[cf. アンチオープ 2001、古谷 2001、萩原 2002]。また、男性不在の家族スタイルは、アフリカ系アメリカ人男性の高い収監率によるものであり、アフリカ系アメリカ人男性が社会、つまり家族、学校、労働、地域社会から孤立する生活環境を再生産していると分析されてきた。よって、男性不在の家族は、女性を世帯主とする家族に顕著な福祉依存、すなわちアフリカ系アメリカ人の家族に特徴的とされる「家母長制」の原因としても説明されてきた。ただし、本発表で注目しておきたいのは、現代米国においていまだ正常な家族像として提示される「(白人の)伝統的家族」は、奴隷制度から生じた人種的、性的、社会経済的な環境なしには成立しえなかったということである。
こうした家族の「問題」にたいして、アフリカ系アメリカ人の社会運動はどのように対処してきたのか。アフリカ系アメリカ人の社会運動や社会文化活動〈全国黒人実業連盟NNBL、公民権運動、ブラック・モスレム(ネイション・オブ・イスラム)、ブラック・パワー運動、クワンザーアKwanzaa〉にみられる対処法は、「モイニハン・レポート」(1965)と通底する部分が多い。これは、端的に言えば、アフリカ系アメリカ人の家族にまつわる問題を解決するには、家父長制にもとづいた家族を形成する必要があり、そのためにはアフリカ系アメリカ人男性の「男らしさ」を醸成しなければならない、というものである。しかしながら、公民権運動以降、おもにアフリカ系アメリカ人女性のなかで、アフリカ系アメリカ人の家族問題を改善する策として家父長制に過度に傾倒することにたいして批判の声があがっている[hooks 1992、萩原 1997、cf. Girloy 2000、風呂本 2003、フックス2010(1981)]。
本発表では、オリシャ崇拝運動にみられる宗教的疑似家族や、家族に関する価値観、性役割、性規範などを取り上げ、運動が紡ぐ縁がアフリカ系アメリカ人の家族問題、すなわち性の逸脱や男性の社会からの孤立化とどのように関わっているのかを考えたい。オリシャ崇拝の家族や性にまつわる特徴は、大きく分けて三つある。⑴性ではなく、司祭歴をもとにした階級制度と宗教的疑似家族の形成、⑵一夫多妻制とその解釈にみられる男女差、⑶性を受容する価値観(非-禁欲主義)である。これらの特徴によって、オリシャ崇拝運動の女性成員は従属的な地位に甘んじることなく、家父長的な社会運動そのものを変革しながら運動に従事している。これは結果として、男性成員に「男らしさ」を求め、それにもとづいて家父長的な家族を形成するという価値観や自由労働イデオロギーから男女双方の成員を限られた領域においてではあるが解放することにつながっているといえる。
男性同性間の性関係からパートナーシップへ
新ヶ江 章友
名古屋市立大学看護学部
本発表では、「ゲイ」ゆえに日本社会から孤立しているという考え方を前提とはしない。なぜなら、「ゲイ」同士の関係はときとして親密であり、このような関係は必ずしも彼らを孤立状況に追い込んだりはしないからである。しかし一方で、「ゲイ」の友達はいらない、男とセックスさえできればいいという考え方や行動をする「ゲイ」もいる。このような態度が、その「ゲイ」自身を孤立に追い込んでいるのではないかという論理で本発表は構成される。ここで着目したいのは、日本在住「ゲイ」の性的欲望と主体化の問題である。権力によって性的欲望がどのように煽られ、どのような「ゲイ」という主体が形成されているのか。なぜ「ゲイ」同士の友達関係は形成しにくいのか。性行為を伴わない「ゲイ」同士の友達関係の形成が、どのように権力への抵抗となりうるのかを吟味してみたい。
発表の構成としては、まずフーコーの権力と性的欲望に関する議論を主体化と統治性と関連付けながら整理し、権力への抵抗としての「友情」について言及した。ここから、日本の「ゲイ」男性の性的欲望が駆り立てられていく社会・文化的背景について、日本の「ゲイ・ビジネス」について紹介した。ここでいう「ゲイ・ビジネス」とは、具体的にはゲイバー、ゲイ向けDVD、「ハッテン場」、ゲイ雑誌、「ウリ専」などをさす。また近年では、インターネットの出会い系サイトやスマートフォンのアプリなど最先端の技術を駆使しながら、「ゲイ」同士の出会いの機会は著しく増加してきている。日本の「ゲイ・ビジネス」は、ライフスタイル提供型の西欧の「ゲイ・ビジネス」と比較すると性的なものに特化する傾向が顕著であり、性的欲望を満たすという点において不自由感はあまりないという日本在住「ゲイ」男性の語りを紹介した。このように高度に発達した「ゲイ・ビジネス」を背景としながら、日本の「ゲイ」同士の関係は性的関係に流れがちで、長期的な人間関係が築きにくい。つまり、友達と恋人の境界が曖昧になりがちで、体だけの関係で終始することも多い。しかし、権力によって駆り立てられる性的欲望に忠実に従うことは、必然的にHIV感染リスクを高めることにもなる。性的欲望を駆り立てる権力へと抵抗していく手段として、「ゲイ」同士の「友情」の問題―つまり、性的関係のみに終始しない人間関係の構築―が考えられる。日本において、ゲイ・アクティビズムをはじめとする「ゲイ」同士の連帯が困難な背景の一つとしては、この性的欲望を駆り立てる「ゲイ・ビジネス」の高度な発展があると考えられる。以上のような日本在住の「ゲイ」男性の人間関係の構築は、日本においてMSM間でのHIV感染が広がっている背景を知る上でも重要であり、また日本在住「ゲイ」男性の視点を通して、日本社会における性的欲望の配置のされ方、国家との関係、家族などのあり方を逆照射する「クィア」な視点からの分析も今後さらに必要となる。
DATE : 2013.03.04

Copyright (c) Tokyo University of Foreign Studies. All Rights Reserved.
AA研共同研究プロジェクト




